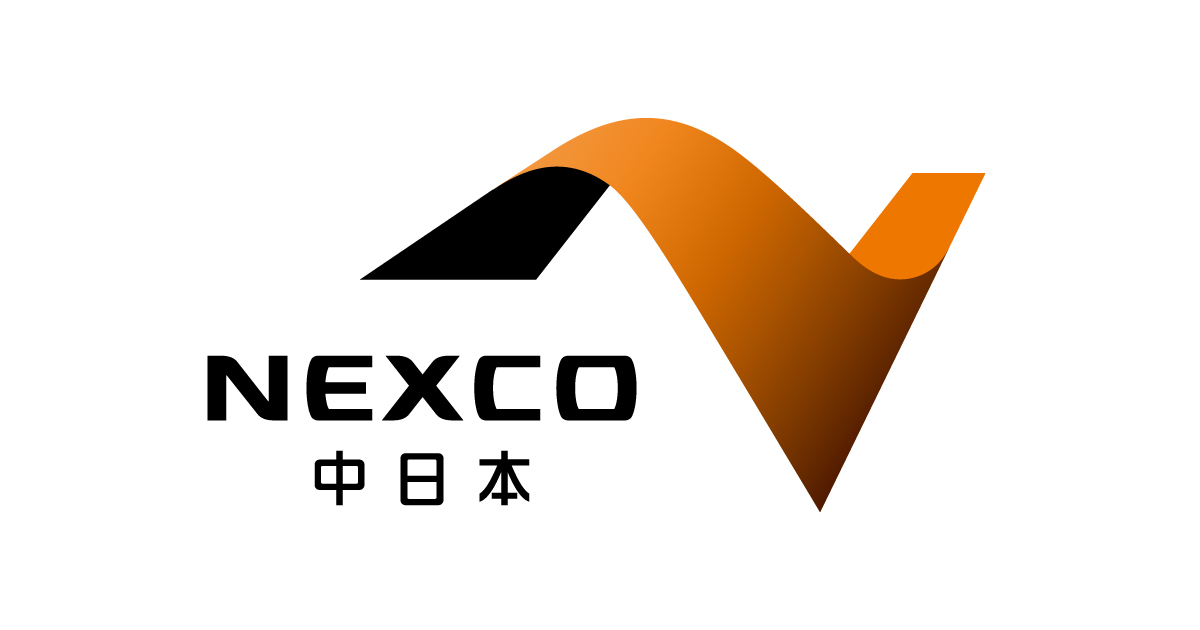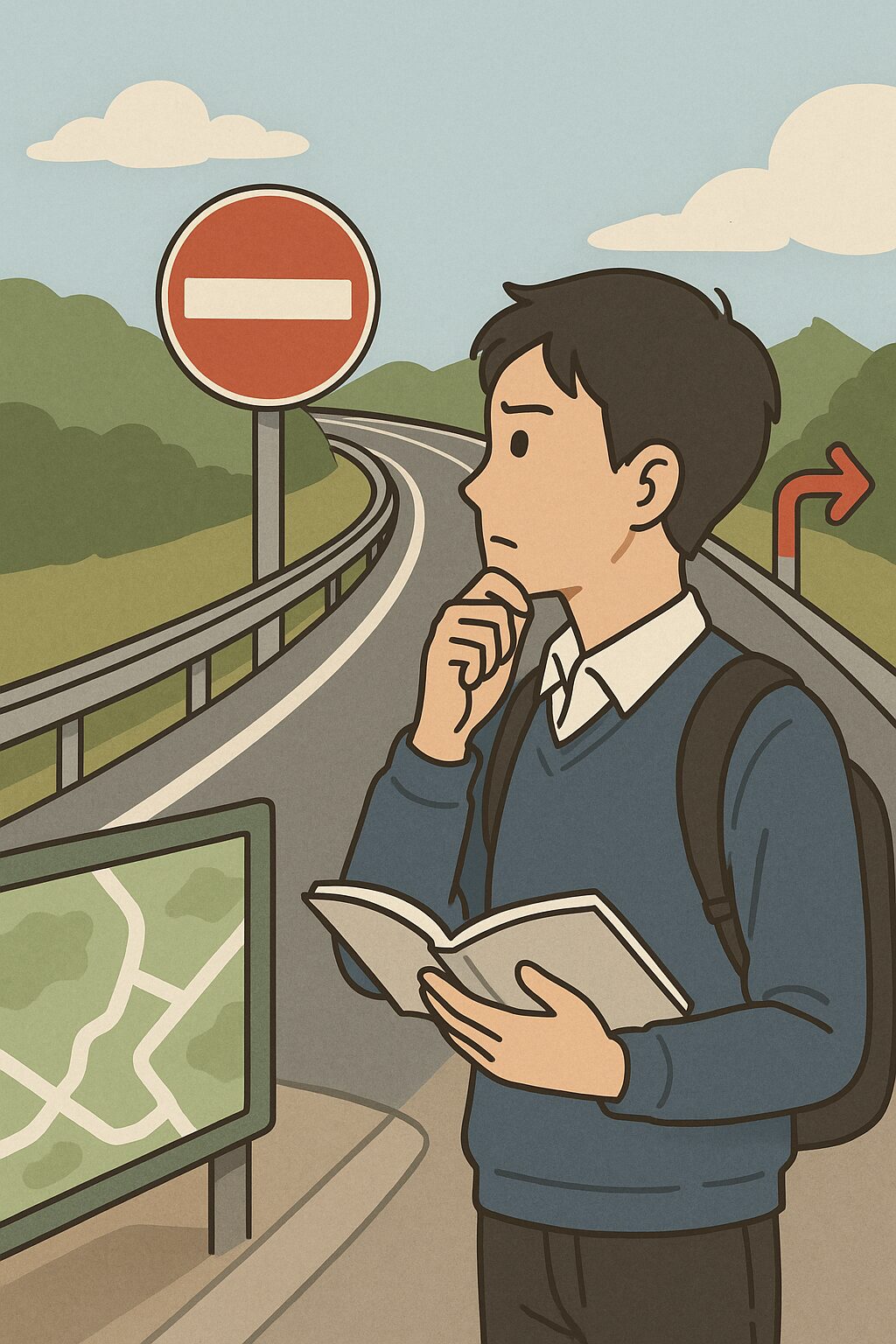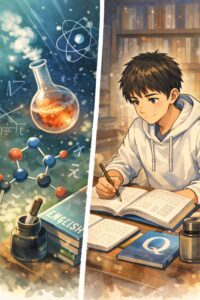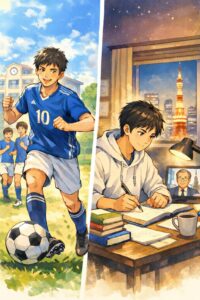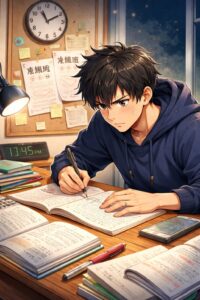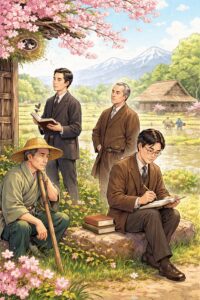「逆走している人ほど、“まっすぐ進んでいる”と思っている」――その思い込みがミスを生む
◆「まっすぐ走っていたはずなのに…」
5月18日(日)の午前、新名神高速道路で逆走車による事故が起きました。場所は三重県亀山市。私も出張などでよく通るルートです。
ニュースによると、青い乗用車が下り線を約10kmも逆走し、複数の車両に接触。幸いにも、命に関わるような大きなケガはなく、4人が軽傷で済んだとのことでした。
それでも、「逆走」という文字を見たとき、私は背筋がゾッとしました。
なぜなら、運転していた本人は「逆走している」という自覚がなかった可能性が高いからです。
◆勉強でも「逆走」は起きている?
実はこの「気づかない逆走」、教育の場にも似たようなことがあると感じています。
例えば――
- 数学の難問に取り組む生徒が、「この公式で解けそう!」と思って進んだのに、なぜか最後で大きく間違える
- 現代文の選択肢問題で、「これが正解に見える」と選んだのに、解説を読むと全然違った
そうしたとき、生徒は言います。
「え、でもこれで合ってると思ってました」
「間違ってるって言われても、なんでなのか分かりません」
これはまさに、“逆走しているのに、それに気づかない”状況そのものです。
◆“違和感”に立ち止まれるかどうか
勉強において最も怖いのは、「分かったつもりになっている」状態です。
- 本当は誤解しているのに、「こういう問題だ」と思い込んで突き進んでしまう
- 選択肢を雑に読んで、「だいたい合ってる気がする」と判断してしまう
このとき、必要なのは「あれ?ちょっと変だな?」という“違和感”に気づく力です。
その力がある子は、一度立ち止まり、別の道を探そうとします。
でも、その力が育っていない子は、まっすぐ進み続けてしまうのです。
◆現代文・数学――“逆走”に強いのはこんな子
現代文が強い子は、「筆者の主張」を読んでいて違和感を抱いたときに、「本当にそう言ってるか?」と本文に立ち返ります。
数学が強い子は、「この公式でいけそう」と思ったあとで、条件をしっかり確認し、「このやり方でズレが出ていないか?」をチェックします。
こうした子どもたちは、“道を間違えること”よりも、“間違ったまま進むこと”を怖がっているのです。
◆間違えるのは誰にでもある。問題は「気づけるかどうか」
人間ですから、間違いはあります。
でも、それに“自分で気づけるか”が、その後の成長に大きな差を生みます。
新名神で逆走していた車のドライバーも、もしかしたら「自分は正しく走っている」と思い込んでいたのかもしれません。
これは勉強でも、生活でも、同じ。
- 自分が「正しい」と思っていても、周囲の反応とズレていたら、立ち止まる勇気が必要
- 「先生の説明、ちょっと分からなかったかも」と感じたら、その違和感を放置しないこと
◆学びの姿勢とは、「方向を確認すること」
私たちは生徒たちに、ただ知識を詰め込むのではなく、「今、自分は正しい方向に進めているか?」を自分で確かめられる力を育ててほしいと願っています。
だからこそ、質問する力、間違いを直視する力、そして「もう一回やってみよう」と言える勇気を大切にしているのです。
◆おわりに:逆走しないために
今回の事故では、大きな命の犠牲が出なかったことが本当に救いでした。
でも、私たち一人ひとりが「逆走しない力」「気づく力」を持つことが大切だと改めて思わされました。
勉強でも人生でも、間違うことはあります。
でも、その間違いに“途中で気づける人”になってほしい――そんな願いを込めて、この記事を書きました。
高速道路の逆走に関するリンク先