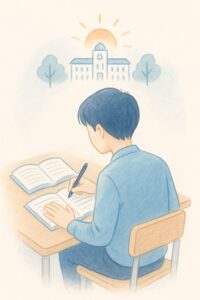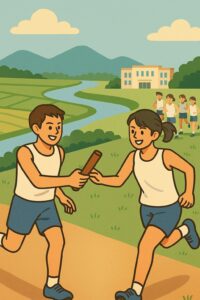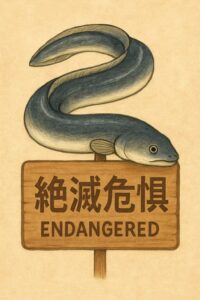「高校生先生」に教わるという体験
2025年7月25日付の中日新聞北勢版に、こんな素敵な記事が掲載されていました。
舞台は四日市市立大池中学校。夏休みに行われた「補充学習会(地域子ども教室)」で、地元の高校生たちが“先生”となり、後輩である中学生に勉強を教えるという取り組みが紹介されていました。
参加したのは、川越高校や四日市南高校、四日市メリノール学院高校に通う高校生たち。その多くが、大池中の卒業生です。生徒数40名に対して、11名の高校生ボランティアが加わるという、まさに“縦のつながり”が実現された学びの場でした。
「先輩の姿から学べる学校」――学校ビジョンに基づいた挑戦
この補充学習会は、大池中学校が2025年度から掲げる教育ビジョン「先輩の姿から学べる学校」を具体化したものです。
- 3年生の姿を1・2年生が学ぶ。
- 卒業生である高校生から在校生が学ぶ。
そんな“人を通して学ぶ文化”を育むために、学校側は今年度から意図的に縦の交流の機会を増やしてきました。
今年初めての試みとして、川越高校・四日市南高校に通う卒業生、そして校区内にある四日市メリノール学院の高校生たちが学習ボランティアとして参加。中学生たちは勉強だけでなく、先輩との交流を通じて高校生活への理解も深めました。
中学生の声:「優しかった」「教え方がわかりやすかった」
中学生たちからは、こんな声が寄せられたそうです。
- 「高校生の先輩に聴きやすかった」
- 「いっぱい教えてもらって嬉しかった」
- 「優しかったのでよかった」
- 「わかりやすく教えてもらったから、よくわかった」
- 「高校の話も聞けたからよかった」
これは、単なる学力支援ではありません。心の距離が近い“ちょっと上の先輩”だからこそ生まれる安心感や、学習への前向きな気持ちの変化が見て取れます。
高校生にとっても、学び直しと成長の機会に
一方で、高校生たちも口々に「教えることの難しさ」を実感したようです。
- 「伝えるって難しい」
- 「どうしたら分かってもらえるかを考える中で、自分も学べた」
- 「教えることで中学内容の大切さを再確認できた」
ふだん難解な高校課程を学んでいる彼らも、中学内容を“教える立場”として見直すことで、自信を持って指導できたはずです。そして、先生や地域スタッフの姿を見ながら、自分なりの関わり方を模索し、実践する中で人間的にも成長していきました。
教えることで学ぶ、教わることで気づく
「教える経験」を通して学ぶことは、「教えてもらう姿勢」をも変えます。
指導の難しさを知ることで、今度は自分が教わるときに、より主体的に学ぼうとする姿勢が生まれる。
これは教育の理想的な循環であり、生徒間での“相互教育”の価値とも言えるでしょう。
塾でも実感する、「ちょっと上の先輩」の力
千尋進学塾でも、卒業生がふと教室に顔を出し、後輩に勉強を教えたり、進路の話をしてくれたりすることがあります。
そのとき、教わる側の目が輝き、「あの先輩みたいになりたい」という感情が自然に湧き上がる瞬間を、私たちは何度も目にしてきました。
学校の先生や塾の講師ももちろん必要ですが、年の近い先輩との出会いには、何にも代えがたい説得力と親しみがあるのです。
教育とは、「人との関わり」の中で育つもの
今回の大池中学校の取り組みは、地域と学校、卒業生がつながる“学びの文化”のひとつの形です。
知識だけでなく、安心感や憧れ、人間関係の中でしか育まれない力こそが、これからの教育に必要なものだと、改めて感じさせてくれました。
「ちょっと上のお兄さん・お姉さんに教わること」――
その一日が、教わる側にも、教える側にも、一生心に残る学びの原点になることでしょう。
✅ 参考:中日新聞北勢版(2025年7月25日)
✅ 参考:四日市市立大池中学校 公式サイト(2025年7月24日記事)
📎 大池中学校の記事はこちら