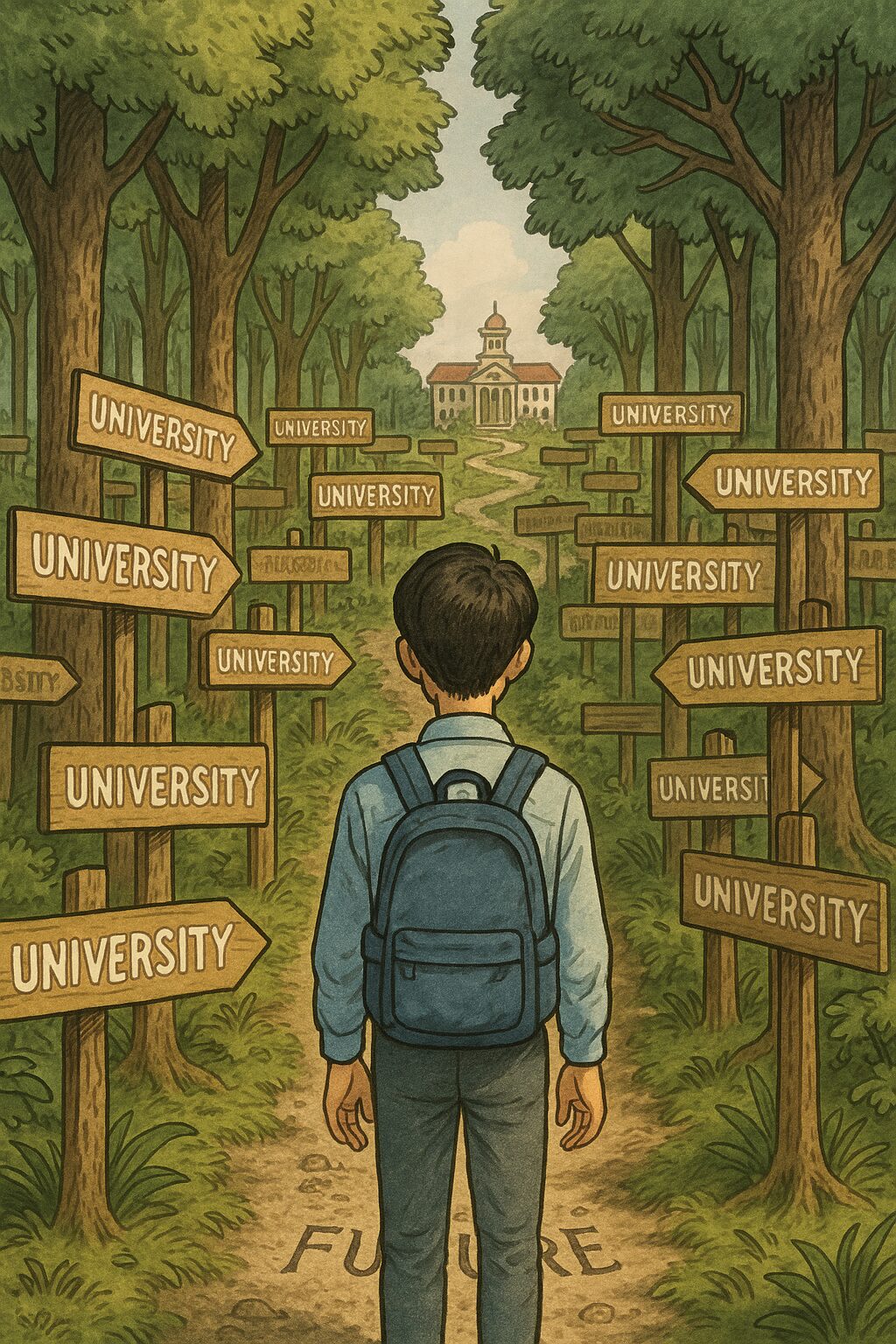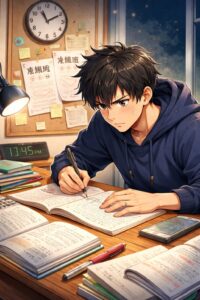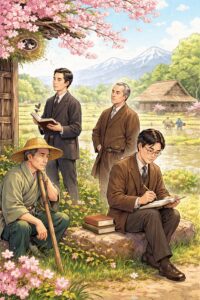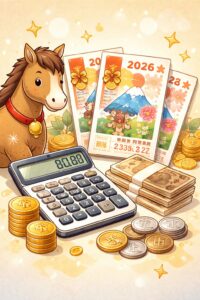「大学の数が多すぎる」「どこかには入れるから安心」という声を聞くたびに、私はある違和感を覚えます。
今、日本には800以上の大学が存在します。けれども、増えた数に比例して「本当に学びたい学生」は増えたのでしょうか。今日は、塾の現場から見える実態をもとに、この問題を考えてみたいと思います。
なぜこんなに大学が増えたのか?
1990年代以降、大学設置基準の緩和や少子化を見越した進学率向上政策のもと、多くの大学が新設されました。とくに地方では、若者の流出を防ぐ目的で大学が誘致されるケースも多くありました。
しかし、その裏には、大学を“教育機関”としてではなく、“地域振興装置”や“天下り先”として見ていた大人たちの存在も見え隠れします。
大学に行く意味、考えたことはありますか?
私は多くの高校生・保護者と面談してきました。「とりあえず大学に行く」「みんな行くから」という理由で大学進学を考えている人の、なんと多いことか。
あなたの子はどの大学に行くのか、より「なぜ大学に行くのか」を考えてほしい。
時間とお金の重み
大学は、学費だけでなく、若者の「4年間」という人生でもっとも貴重な時期を預かる場所です。そしてその期間、彼らは基本的に“労働者”ではなくなります。
労働力人口の減少が叫ばれる中、若者が責任を負う立場から離れてしまうことが、果たして社会全体の利益につながるのか、私は疑問を抱いています。
責任ある立場――たとえば仕事――に身を置いてこそ、人は本気で成長できます。ところが、今の大学生の多くは、責任のない立場に甘んじています。保護者に依存し、アルバイトにも本気になれない。その結果、社会に出る時に「ゼロからスタート」になってしまうのです。
税金の使われ方と国益の損失
私立大学にも、国からの助成金が使われています。つまり、大学が増えるほど、税金の分配先が増えているということです。
「大学が増えれば進学の機会が増える」というのは一理ありますが、それが本当に“国益”になっているかを問う必要があります。
本当に学びたい学生に資源を集中させるべきであって、「なんとなく大学に行く」人のために税金を使うのは、健全な国家運営とは言えないでしょう。
もし大学の定員が絞られたら?
仮に、大学に“全員が行けない時代”が再び来たとしたらどうなるでしょうか。
- 高校生たちは、もっと真剣に勉強に取り組むようになるでしょう。
- 浪人してでも挑戦する価値がある大学が増えるでしょう。
- 大学は“高度な知の拠点”として、本来の機能を取り戻すかもしれません。
そしてそれは、高校・中学・小学校の学びをより真剣にさせる契機にもなるはずです。
大卒資格が形骸化していないか?
「大卒資格が取れるから看護大学へ」「四大卒の方が就職で有利だから」――こうした理由で専門職養成の大学に進学するケースも増えています。
もちろん、進路は多様であるべきです。大学に通い、学費を払って学び、学位を取得するという選択自体は尊重されるべきものです。ただ、看護師や保育士、技術職などの中には、高校や専門学校でも十分に資格取得が可能なものもあります。
大学という選択肢が唯一無二ではないことも、知っておいて損はないでしょう。目的に応じて、進路を柔軟に考えることが求められている時代だと思います。
淘汰の時代へ
学習塾も同じです。少子化の中、生き残っていく塾は限られています。私たちの周囲でも多くの塾が撤退しました。
大学もまた、厳しい競争に晒されるべきです。それは単なる広告やマーケティングでの競争ではなく、「本物の学び」「研究成果」「社会への貢献」で評価されるべきです。
大学が与えてくれる“遠回り”という価値
大学に行くことで、人生において遠回りができるという側面もあります。自分が得意でない教科に取り組んだり、興味のない分野の必修科目でテストを受けたりと、回り道のような経験をすることもあります。
しかし、そうした遠回りこそが、将来の思考の幅や判断の深さにつながることも少なくありません。いわば「急がば回れ」です。大学は、そういった“ゆとり”や“余白”、そして“遠回りの時間”を提供してくれる、貴重な場であるとも言えるでしょう。
結びに――進学とは、“選ぶ”ことではなく、“意味を問う”こと
大学の数が多いことが悪いとは限りません。しかし、「大学に行く意味」を見失ったまま進学しても、得られるものは限られています。
千尋進学塾では、受験のための学力をつけるだけでなく、「その先にある人生」についても、しっかり考える指導を行っています。
もし、この記事が少しでも「考えるきっかけ」になれば幸いです。