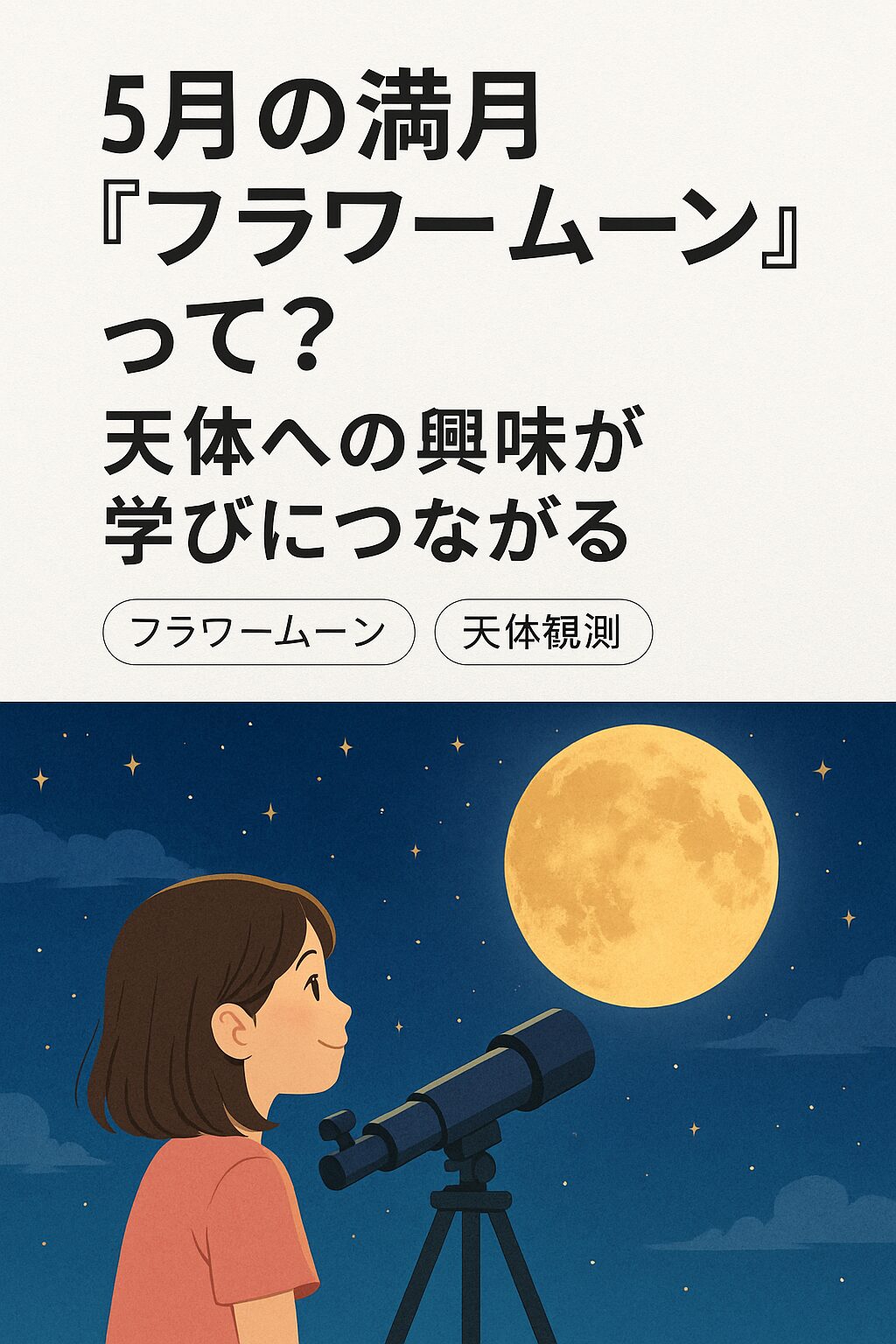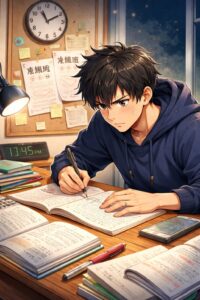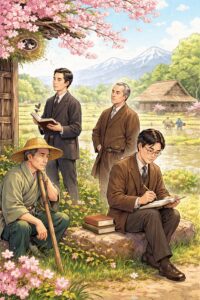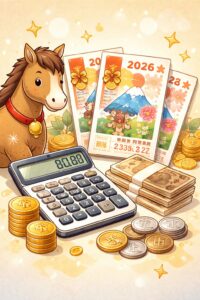📚「差のつく!読解のチカラ育成講座シリーズ」記事一覧
- ① “国語が苦手”は勘違い?読解力の正体、教えます
- ② “読めてるつもり”が一番危ない!読み飛ばし世代に欠けている力
- ③ 応用問題が解ける子の秘密は“読む力”にあった!
- ④ 読解力は国語だけの話じゃない!算数・理科にも効く“読みの技術”
- ⑤ 説明文が苦手な子に足りないのは“読書”じゃなく“論理力”
- ⑥ 小論文・推薦入試で差がつく!読解力×論理力の真価とは
- ⑦ 本を読むだけでは“読解力”は育たない?間違った読解力の鍛え方
- ⑧ “選択肢の消去法”で点が取れない子へ。論理的に読む力、ついてますか?
- ⑨ 読解力は“後からでも”伸ばせる?苦手意識をひっくり返す塾のトレーニング
- ⑩ 読解力と成績の相関関係|トップ層が必ず持っている“読みの技術”
5月の満月「フラワームーン」って? 天体への興味が学びにつながる
令和7年5月13日(火)午前1時56分──この時間、空にはまんまるの満月が浮かび上がります。 5月の満月は「フラワームーン(Flower Moon)」と呼ばれ、春の花々が咲く季節を象徴する名前がついています。 そんな満月の話題は、実は中学3年生の理科「天体分野」と深く関係しています。
「満月」ってどんなときに見えるの?
満月とは、地球から見て「太陽-地球-月」の順に一直線に並んだとき、月の全面が太陽の光で照らされて明るく見える現象です。 この位置関係は中3理科の定番単元。実際の満月を眺めながら、「今、地球と月と太陽はどう並んでいるのかな?」と想像することも、立派な“理科的思考”なのです。
フラワームーンとは?
「フラワームーン」はネイティブ・アメリカンの風習が語源で、5月に咲く多くの花々にちなんで名付けられました。 月には「ストロベリームーン(6月)」「ハーベストムーン(9月)」など、季節ごとにさまざまな名前がついています。 こうした呼び名を知るだけでも、自然や文化に興味を持つきっかけになります。
天体は“科学への入口”
夜空を見上げること──それは、科学の第一歩です。 「どうして月は満ち欠けするの?」「月と太陽はどう動いているの?」そんな素朴な疑問が、やがて学びの動機になります。 中学3年生の理科では、月の満ち欠け、太陽と月の見かけの動き、地球の自転・公転などを扱います。 実体験とつなげて学ぶことで、理解もぐんと深まります。
塾としてできること
千尋進学塾では、学校の教科書内容をベースにしながらも、「今、話題になっていること」や「実際に体験できること」とリンクさせて、授業を展開しています。 机の上だけでなく、空を見上げるような学びを大切にする──それが、子どもたちの学習意欲や探究心を育てると信じているからです。
今年のフラワームーン、ぜひご家庭でも空を見上げてみてください。 「なぜ満月になるの?」「どっちから月が昇ってくる?」そんな問いかけが、明日の学びへの橋渡しになりますように。
\自然へのまなざしが、学ぶ力を育てます/