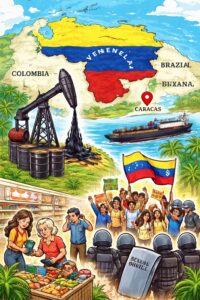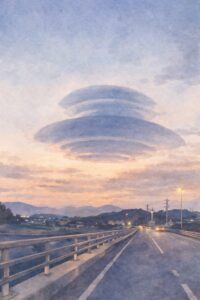大学とは何か?— 今こそ立ち返りたい、学びの原点
はじめに:大学改革が話題になる今、改めて考えたいこと
最近、「大学の授業時間が延びる」「学費が上がる」「共学化するかどうか」など、大学に関するニュースが増えてきました。そんな中で、ふとこんな疑問を持った方も多いのではないでしょうか。
「そもそも、大学って何のためにあるの?」
塾で高校生と向き合う私たちも、実はこの問いに向き合うことが少なくありません。
大学とは何か?歴史的・理念的な原点
大学という言葉は、古代ヨーロッパの「ユニヴェルシタス(universitas)」に由来し、「知を追求する共同体」という意味があります。中世ヨーロッパの大学は、宗教や政治から自由であること、つまり「学問の自由」が何よりも大切にされていました。
日本でも、戦後に設立された多くの大学は、教育基本法や憲法に基づき「学問の府」としての役割を与えられています。大学の役目は、単に資格を取ったり、就職のために通うだけではないのです。
高校・塾との違い:教えてもらう場から、自ら学ぶ場へ
高校や塾は「受け身の学び」が中心です。先生が教えてくれて、テストで点を取ることがゴールになります。
一方、大学は「自分で問いを立て、自分で調べ、仲間と議論する」場所です。教科書も正解もない中で、学問という「探究の旅」に出かけることが本質です。
学問の自由と大学の自治:なぜそれが重要なのか
最近、「大学改革」の名の下に、大学が企業のような存在になってきているという声があります。たしかに経営効率や時代の変化に対応することは必要です。
しかし、学問とは「効率」や「収益」で測れない価値を持っています。大学が独立した存在であること(=大学の自治)は、知の自由、批判精神、多様性を守るために不可欠です。
「就職予備校」ではない、大学の本来の価値とは
進学説明会で「この大学は就職に強いですか?」という質問をよく受けます。もちろん大切な観点ですが、大学の価値は就職率だけでは測れません。
むしろ、4年間で「何を学び、どう変わったか?」が、その人の人生にとっての大学の価値になります。今は答えがない時代だからこそ、「考える力」が問われています。
おわりに:今を生きる高校生へ伝えたいこと
これから大学を目指す君へ。「大学に行く意味」を誰かに決められる必要はありません。ただ、立ち止まって考えてみてください。
君は、何のために学びたいのか?
答えはまだなくていい。でも、その問いを持ち続けてほしい。私たちは、その問いに寄り添う塾でありたいと願っています。
追記:個人的な見解
もちろん、私は個人的には、大学が就職予備校のような役割を担うことも、ある程度は仕方のないことだとも思っています。社会の変化、経済的な現実、若者のキャリア形成の難しさを考えれば、「学び」と「仕事」がつながることは決して悪いことではありません。
しかしそれでも、大学には「それだけではない価値」があることを、私たち大人が忘れてはいけないと強く感じています。
📚「差のつく!読解のチカラ育成講座シリーズ」記事一覧
- ① “国語が苦手”は勘違い?読解力の正体、教えます
- ② “読めてるつもり”が一番危ない!読み飛ばし世代に欠けている力
- ③ 応用問題が解ける子の秘密は“読む力”にあった!
- ④ 読解力は国語だけの話じゃない!算数・理科にも効く“読みの技術”
- ⑤ 説明文が苦手な子に足りないのは“読書”じゃなく“論理力”
- ⑥ 小論文・推薦入試で差がつく!読解力×論理力の真価とは
- ⑦ 本を読むだけでは“読解力”は育たない?間違った読解力の鍛え方
- ⑧ “選択肢の消去法”で点が取れない子へ。論理的に読む力、ついてますか?
- ⑨ 読解力は“後からでも”伸ばせる?苦手意識をひっくり返す塾のトレーニング
- ⑩ 読解力と成績の相関関係|トップ層が必ず持っている“読みの技術”