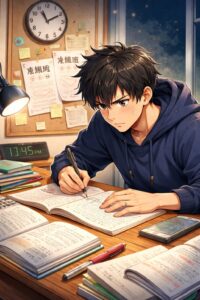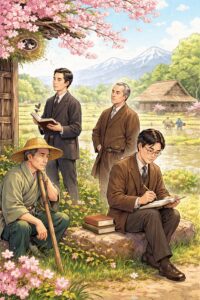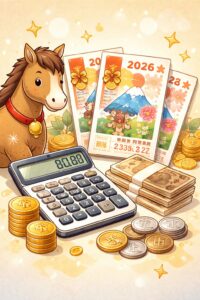本稿では、子どもたちと一緒に「自然と人の共生」を考える題材として、 クマの暮らし(冬眠・子育て・人との距離感)を取り上げます。 自然の仕組みを知ることは、学習への関心や観察力・安全意識の醸成につながります。
三重県桑名市の塾/予備校【千尋進…


🌲 森のクマさんのおはなし(子ども向け) | 三重県桑名市の塾/予備校【千尋進学塾】|桑名高校・四日市高…
やあ、こんにちは。ぼくは森のクマさんだよ。きょうは、ぼくたちのくらしをしょうかいするね! ❄️ ふゆは「ながーいおひるね」 ふゆになると、もりにはごはんがすくなくな…
目次
❄️ クマの冬眠 ― 理由は「寒さ」ではなく「食べ物不足」
- 冬は餌が少ないため、エネルギー節約のために冬眠します。
- 心拍や呼吸をゆるやかにし、蓄えた脂肪で乗り切ります(完全に眠り切るわけではなく、危険を感じれば覚醒)。
学びのポイント:「必要に応じて戦略を変える」自然の合理性は、勉強の計画立案にも通じます。
👶 赤ちゃんクマの子育て ― 守り抜く力
- 出産は冬眠中(1〜2月頃)。生まれたては約300gと小さく、春まで母乳で成長します。
- 母子は約1年半〜2年行動を共にし、採餌や危険回避を学びます。
- 子連れグマは防衛本能が強く、接近は禁物です。
学びのポイント:「守るべき目的」が行動を強くする。目標設定の重要性を子どもと共有できます。
🤝 人とクマの安全な距離の取り方
- 音で存在を知らせる:クマ鈴・ラジオ・会話。
- 匂いを残さない:食べ物・ゴミは密閉&持ち帰り。庭木の実は早めに収穫。
- 遭遇したら:走らず、背を向けず、ゆっくり後退。木や岩を間に。
学びのポイント:「思いやりの工夫」が共存の第一歩。学校生活の人間関係にも応用できます。
🌍 世界の多様なクマたち
- ツキノワグマ:日本のクマ。胸の三日月模様。木登り・木の実が得意。
- ホッキョクグマ:北極圏。アザラシ中心の食性。体格最大級。
- グリズリー(ヒグマ):北米。サケ漁で有名。警戒心が強い。
- ジャイアントパンダ:中国。主食はタケ。生態が特異で人気。
学びのポイント:環境に応じた多様性を理解することは、子どもの視野を広げます。
🌲 千尋進学塾から
私たちは学力の向上と同時に、「観察→仮説→検証」の姿勢や、多様性への理解を大切にしています。 自然の学びは、探究学習や進路選択にも活きます。
次回は「もし日本にヒグマが来たらどうなる?」をテーマに、リスクコミュニケーションや情報リテラシーも含めて考えます。
参考にしたページ
クマについてよくあるご意見・ご質問(秋田県庁 地域振興局)
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/85123
📚「差のつく!読解のチカラ育成講座シリーズ」記事一覧
- ① “国語が苦手”は勘違い?読解力の正体、教えます
- ② “読めてるつもり”が一番危ない!読み飛ばし世代に欠けている力
- ③ 応用問題が解ける子の秘密は“読む力”にあった!
- ④ 読解力は国語だけの話じゃない!算数・理科にも効く“読みの技術”
- ⑤ 説明文が苦手な子に足りないのは“読書”じゃなく“論理力”
- ⑥ 小論文・推薦入試で差がつく!読解力×論理力の真価とは
- ⑦ 本を読むだけでは“読解力”は育たない?間違った読解力の鍛え方
- ⑧ “選択肢の消去法”で点が取れない子へ。論理的に読む力、ついてますか?
- ⑨ 読解力は“後からでも”伸ばせる?苦手意識をひっくり返す塾のトレーニング
- ⑩ 読解力と成績の相関関係|トップ層が必ず持っている“読みの技術”