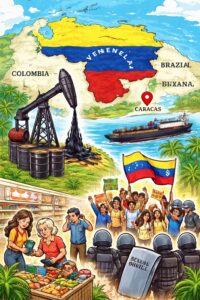期末テスト前夜に“いま”やるべき最終チェック(数学A・論理表現)
明日は桑名高校1年生の期末テスト。
今回の範囲は、数学A・論理表現ともに内容が濃く、得点差がつきやすい単元が並んでいます。
「どこを優先して見直せばいいのか」
「何を間違えやすいのか」
この2点を、教室として“実戦目線”で整理しました。
直前の限られた時間だからこそ、要点だけに絞って仕上げてください。
■ 数学A:図形を扱う問題で差がつく
1. 方べきの定理・接弦定理
今回のテスト範囲の中心です。
結論からお伝えすると、図の見え方に惑わされず、等式を正しく立てられるかどうかが勝負になります。
- 割線×割線:AP×AQ = BP×CQ
- 接線×割線(接弦定理):接線の長さ2 = 外分 × 全体
- 逆の利用:
- 長さが等しい → 「接線である」
- 積が等しい → 「円に属している」
式が一つ立てば7割が決まります。迷ったらまず式だけ書く、これが最短ルートです。
2. 円の共通接線
外側(外接)か内側(内接)かで公式が変わるため、正確な判別が必要です。
- 外接:L2 = d2 − (r1 − r2)2
- 内接:L2 = d2 − (r1 + r2)2
特に「片方がもう片方の中にある」ように見える図は要注意。
図の印象に引っ張られず、半径と距離 d の関係で決めてください。
3. 円に内接する四角形
ここは“対角の和=180°”とその逆、この2つだけ確実に覚えておけば十分得点できます。
- 和が180° → 内接四角形
- 内接四角形 → 和が180°
面積問題では、三角形への分割も頻出です。
4. 約数
最後に“計算力の貯金を作る単元”です。
- 素因数分解
- 指数+1 の積で約数の個数
- 必要に応じて公約数・公倍数
作業自体は単純ですが、素因数分解に時間がかかると焦りが出ます。
今日は“3〜4問だけテンポよく解く”ことをおすすめします。
■ 論理表現(英文法):3単元の基礎で決まる
1. 関係詞
まずは、以下を正しく見極められれば十分です。
- 主格(who / which)
- 目的格(whom / which)
- 所有格(whose)
- 関係副詞(where / when / why)
thatへの置き換え
判断基準はシンプルで、「節の中の動詞の数を見る」ことです。
動詞が足りない → 主格
動詞が揃っている → 目的格
この癖をつけると正答率が一気に上がります。
2. 比較
今回の英文法でもっとも得点しやすい分野です。
- 原級:as 〜 as …
- 比較級:〜er than …
- 最上級:the + 最上級
- 強調:much / far / a lot
- as の後ろは必ず原級
形だけ覚えれば確実に取れるので、今日は典型問題だけ確認してください。
3. 仮定法の基礎
入門レベルでの出題が想定されます。
- 仮定法過去:If + 過去形, would + 動詞の原形
- 仮定法過去完了:If + had p.p., would have p.p.
- should / could / might への書き換え
「現実と違うことを言うときは時制が一つ下がる」と理解しておけば、迷いません。
■ 最後の60分で仕上げる方法
数学A(45分)
- 方べきの定理(3パターン)を空書き3周
- 外接/内接の判定だけ集中して3問
- 内接四角形の「逆」を使った典型問題を1問
- 素因数分解から約数の個数を3問
論理表現(15分)
- 関係詞の主格/目的格だけ絞って練習
- 比較の原級・最上級の確認
- 仮定法の2パターン(過去/過去完了)の仕訳
■ 明日のテストで気をつけたい5つのポイント
- 接弦定理で「外 × 全体」を逆に書かない
- 内接四角形の“逆”を忘れない
- 関係詞は節の中の動詞チェックを徹底する
- 比較で as の後ろに比較級を置かない
- 仮定法は“今の話か・過去の話か”で時制を決める
■ 最後に
期末テストは、これまでの学習を整理し「自分の現在地」を確認できる貴重な機会です。
前夜に慌ててすべてを詰め込む必要はありません。
「どこを落とさないか」。
この一点を意識するだけで、得点は安定します。
明日の健闘を、教室一同、心から願っています。
📚「差のつく!読解のチカラ育成講座シリーズ」記事一覧
- ① “国語が苦手”は勘違い?読解力の正体、教えます
- ② “読めてるつもり”が一番危ない!読み飛ばし世代に欠けている力
- ③ 応用問題が解ける子の秘密は“読む力”にあった!
- ④ 読解力は国語だけの話じゃない!算数・理科にも効く“読みの技術”
- ⑤ 説明文が苦手な子に足りないのは“読書”じゃなく“論理力”
- ⑥ 小論文・推薦入試で差がつく!読解力×論理力の真価とは
- ⑦ 本を読むだけでは“読解力”は育たない?間違った読解力の鍛え方
- ⑧ “選択肢の消去法”で点が取れない子へ。論理的に読む力、ついてますか?
- ⑨ 読解力は“後からでも”伸ばせる?苦手意識をひっくり返す塾のトレーニング
- ⑩ 読解力と成績の相関関係|トップ層が必ず持っている“読みの技術”