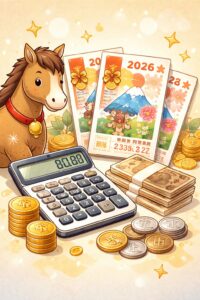前回の記事では、アメリカの関税政策によってアフリカの小国・レソトがどれほど大きな打撃を受けたかをお伝えしました。
今回は、そこからもう一歩踏み込みます。
「では、レソトのような小国はどうすれば“大国の都合”に振り回されず、自らを守ることができるのか?」
そんな問いに、一緒に向き合ってみたいと思います。
🗺️ 小国であるという“宿命”
まず、前提として押さえておきたいのは、小国は構造的に「不利」であるという現実です。
- 市場が小さい → 外資の関心が薄い
- 交渉力が弱い → 国際的影響力が乏しい
- 産業基盤が脆弱 → 一つの政策で壊滅的被害を受ける
こうした中で「自らを守る」ためには、以下のような戦略的視点が求められます。
🛡️ 小国の自衛戦略①:地域連携で“声の集約”を図る
レソトは「SACU(南部アフリカ関税同盟)」の一員です。
小国単独では相手にされにくい交渉も、「共同体」として声を上げることで交渉力を高めることが可能になります。
事例:カリブ海の小国群(CARICOM)が国際舞台で共通の立場をとることで、気候変動や貿易政策に一定の影響力を持つようになった例があります。
つまり、小国にとっての防衛は「団結」から始まるのです。
🧠 小国の自衛戦略②:“人的資源”を最大活用する
レソトは人口こそ少ないですが、教育水準は比較的高く、南アフリカで働く出稼ぎ労働者も多くいます。
さらに、アパレル業界での経験・技能を持った人材も豊富です。
提案:これらの人材を活かし、付加価値の高い輸出(知識・ブランド・技術)へと転換していくことが中長期的に必要です。
たとえば、レソト製のエシカルブランドを海外市場に広げるなど、「安価な労働力」からの脱却を目指すことが、国際社会での発言力にもつながります。
🤝 小国の自衛戦略③:国際世論を味方につける
外交とは、政府間交渉だけでなく「世論形成」でもあります。
今回の関税問題も、米国内外でのNGOや報道機関の声がもっと大きければ、違った展開があり得たかもしれません。
行動例:
- 国際ブランド(アパレル・フェアトレード)との連携
- SNSを活用した“草の根外交”
- 世界の教育機関との連携プロジェクト
小国であることは、逆に言えば「共感を得やすい立場」でもあります。
“可視化されにくい痛み”を世界に伝える手段を持つことが、最大の防御になるのです。
🏫 教育の力で“小国の知恵”を育てる
そして、最も長期的かつ確実な自衛策が「教育」です。
- 世界の動きを読み解く力(リテラシー)
- 自国の歴史や立場を伝える力(ナラティブ)
- 状況を転換する構想力(イノベーション)
これらを育む教育こそが、将来の交渉力や自立性を高める“静かな武器”になります。
✍️ まとめ:レソトは“守る”のではなく、“育てる”戦略を
小国は、大国の政策に振り回される存在ではなく、
“戦略を持ったプレーヤー”として育っていく可能性を持っています。
その鍵は、外部とつながること。
そして、自分たちの物語を世界に伝え、価値を創り出すことです。
私たちも、教育を通してその力を育てていきたい。
遠く離れたレソトの話題かもしれませんが、この問いは日本の未来にもきっとつながっています。
📢 関連記事
・🇱🇸 レソトよ、キューバに学べ――“人材が世界に貢献する国”が生き抜く道
▶ https://chihiro-juku.com/2025/07/20/blog/3765/
📰 こちらもおすすめです
・「レソトよ、キューバに学べ――“人を育てて輸出する国”が生き抜く道」
▶ https://chihiro-juku.com/2025/07/19/blog/3753/
📚「差のつく!読解のチカラ育成講座シリーズ」記事一覧
- ① “国語が苦手”は勘違い?読解力の正体、教えます
- ② “読めてるつもり”が一番危ない!読み飛ばし世代に欠けている力
- ③ 応用問題が解ける子の秘密は“読む力”にあった!
- ④ 読解力は国語だけの話じゃない!算数・理科にも効く“読みの技術”
- ⑤ 説明文が苦手な子に足りないのは“読書”じゃなく“論理力”
- ⑥ 小論文・推薦入試で差がつく!読解力×論理力の真価とは
- ⑦ 本を読むだけでは“読解力”は育たない?間違った読解力の鍛え方
- ⑧ “選択肢の消去法”で点が取れない子へ。論理的に読む力、ついてますか?
- ⑨ 読解力は“後からでも”伸ばせる?苦手意識をひっくり返す塾のトレーニング
- ⑩ 読解力と成績の相関関係|トップ層が必ず持っている“読みの技術”