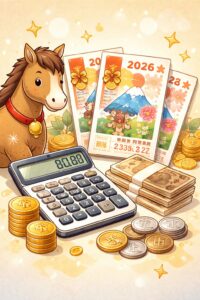「連立政権」とは、複数の政党が協力して一つの内閣を組むこと。戦後の日本政治は、単独政権の安定と、多党が手を取り合う連立のドラマを行き来してきました。本稿は、読みやすいストーリー仕立てで、戦後から現在までの連立政権の歩みを解説します。お子さまとの社会科トークの“きっかけ”にもどうぞ。
戦後直後:協力の出発点(1947–1948)
片山哲内閣 ― 戦後初の本格連立
1947年、衆院選で「どの党も単独過半数に届かず」。そこで、日本社会党の片山哲を首班に、民主党・国民協同党と組んだ連立内閣が発足。占領下の復興・物価対策・労使関係の安定など、課題山積の中で各党が役割分担しながら舵取りを試みました。ただし意見の違いも大きく、約10か月で退陣します。
「55年体制」:長い単独政権の時代(1955–1993)
自民党の一党優位
1955年、自由民主党(自民党)が結成され、社会党が最大野党に。以後約40年、国政の中心は自民党の単独政権が基本に。選挙制度や利益誘導型の政治慣行もあり、連立は表舞台から遠ざかります。経済成長を背景に「安定」を優先する空気が広がった時代でもありました。
体制崩壊と「政変の90年代」(1993–1999)
細川連立(1993) ― “虹の連立”が誕生
1993年、自民党が衆院で過半数割れ。細川護熙を首班に、改革志向の新党や公明、社会など幅広い8党連立が成立します。選挙制度改革(小選挙区比例代表並立制)などを進めつつも、寄り合い所帯ゆえの調整難で短命に。
羽田連立(1994) ― 少数与党の苦難
細川退陣後の羽田孜内閣は、連立崩れで過半数不足となり、わずか2か月で退陣。連立は「数の安定」が命だと、国民に強く印象づけました。
自社さ連立(1994–1995) ― 宿敵が握手
なんと自民党が長年の対立相手だった社会党・新党さきがけと連立を組み、村山富市が首相に。理念の違いを乗り越えた現実路線で、阪神・淡路大震災対応や戦後50年の「村山談話」などに取り組みました。ここから「安定のための連立」という考え方が定着していきます。
「自公連立」の定着と揺れ(1999–)
小渕連立(1999)からの枠組みづくり
景気対策と政権安定を背景に、自民党は公明党(一時期は自由党・保守党も)と協力。2003年以降は自民・公明の二党連立(自公連立)が政治の“基本形”に。公明党は福祉・教育など「生活目線」の政策を推し、自民党の大型政策にブレーキ/アクセルをかける役割を担いました。
民主党中心の連立(2009–2012) ― 二度目の政権交代
2009年、民主党が歴史的勝利。社民党・国民新党と連立を組み、子ども手当や高校授業料無償化などを推進。ただ、米軍基地問題で社民が離脱、東日本大震災対応や消費税をめぐる混乱も重なり、3年余りで幕。日本に「政権交代は起こりうる」という経験を残しました。
第二次安倍内閣以降(2012–2020) ― 長期安定の裏表
2012年以降は自公連立が再び主流に。アベノミクスや安全保障法制など大型政策が進む一方、長期政権ゆえの緩みや不信も指摘されました。以降も自公による政権運営が続きます。
最新局面:自公が「別々の道」へ(2025)
2025年10月、自民党と公明党の連立が解消。約四半世紀にわたり続いたパートナーシップが区切りを迎え、日本政治は新たな連立模索の局面へ。
政治資金をめぐる不信・政策スタンスの溝などから協議が難航し、公明党が連立離脱を表明。自民党は最大政党であるものの、単独では法案・予算の安定運営が難しくなり、新たな連携先の模索が現実的課題に。まさに「連立の再編」が進むタイミングに差し掛かっています。
連立が生まれる“理由”と“コツ”
- 選挙結果の算術:単独過半数に届かないとき、数を積み上げるために連立は不可欠。
- 政策の互補性:大きな政策を進めるには、生活目線の補正(セーフティネット)や合意形成が必要。
- 信頼と手続き:連立合意文書、与党協議会、党首会談などルール化が長続きの鍵。
押さえておきたいポイント
- ニュースの「与党内調整」「与党合意」は、連立政権ならではの大事なプロセス。
- 教育・子育て・税制など家計直結の施策は、連立パートナーの主張が政策に反映されやすい分野。
- 選挙のたびに連立の“組み合わせ”は変わりうる。「誰と誰が組むのか」を見ると先行きが読みやすくなります。
まとめ:連立は「日本政治の当たり前」へ
戦後すぐの協力の出発点、55年体制の単独安定、1990年代の政変を経て、2000年代以降は連立が実務の標準装備に。2025年には長年の自公連立がいったん幕を下ろし、次の“組み合わせ”が問われています。
まるで一つの大きなプロジェクトを、多様な立場の人たちが力を合わせて進めるように、一人では成し得ない課題を協力で動かす――それが日本の連立政治の姿です。変化の中で合意を重ねるプロセスに注目しながら、親子でニュースを読み解いていきましょう。
📚「差のつく!読解のチカラ育成講座シリーズ」記事一覧
- ① “国語が苦手”は勘違い?読解力の正体、教えます
- ② “読めてるつもり”が一番危ない!読み飛ばし世代に欠けている力
- ③ 応用問題が解ける子の秘密は“読む力”にあった!
- ④ 読解力は国語だけの話じゃない!算数・理科にも効く“読みの技術”
- ⑤ 説明文が苦手な子に足りないのは“読書”じゃなく“論理力”
- ⑥ 小論文・推薦入試で差がつく!読解力×論理力の真価とは
- ⑦ 本を読むだけでは“読解力”は育たない?間違った読解力の鍛え方
- ⑧ “選択肢の消去法”で点が取れない子へ。論理的に読む力、ついてますか?
- ⑨ 読解力は“後からでも”伸ばせる?苦手意識をひっくり返す塾のトレーニング
- ⑩ 読解力と成績の相関関係|トップ層が必ず持っている“読みの技術”