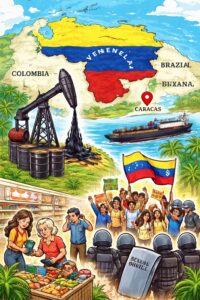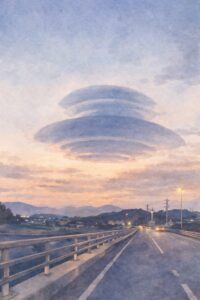東大「カレッジ・オブ・デザイン」新設:学力とユニークさのはざまで
2027年9月、東京大学が約70年ぶりに新設する学部「カレッジ・オブ・デザイン」が注目を集めています。この課程は、文理融合・5年一貫制・全授業英語実施という、従来の学部制度とは一線を画すものです。東大の公式サイトでも詳しく紹介されています(UTokyo College of Design 公式ページ)。
新課程の概要
- 秋入学・5年一貫制(学士+修士)
- 初年度は国内外でのインターンシップや留学を必須化
- 全授業を英語で実施
- 「デザイン」を思考と創造の方法論と捉え、社会課題の解決に挑む
- 入試はエッセイ・面接・英語能力など多面的評価(ルートA/B方式)
「学力」って何?
ここで言う「学力」とは、「学校のテストで点が取れる力」「大学入試模試で結果を出せる力」とします。いわば、知識量と処理能力をベースにした客観的・定量的指標です。
これは公平性の観点から受験制度の根幹を支えてきた指標であり、「誰もが同じ問題で競える」ことが長らく公正性の担保とされてきました。
生のコメントより
この新課程の発表に対し、代ゼミの人気講師・荻野暢也先生は次のように述べています:
定員を増やして、別に枠を作るならいい取り組みだと思うが、より学力が高い生徒がその分、割りを食うのはどうかとは思う。… https://t.co/z9n7OyGcPJ — 荻野 暢也 (@oginonobuya) July 11, 2025
投稿を要約すると…
- 大学入試の定員増や別枠は良いが、学力高い生徒が不利になるのは問題。
- 特定分野で優れた能力の生徒の推薦入学は賛成。
- 近年、推薦入試や女子枠の増加で学力を軽視する傾向がある。
- 大学は学問の場であり、合否は学力で決めるべき。
- 面接やエッセイで能力・人間性を判断するのは困難で公平性に欠ける。
- 学力に代わる公平な評価基準が見当たらない。
- 大学受験は誰にとっても平等なチャンスであるべきだが、最近その原則が揺らいでいる。
- (PS)議論は一般学生ではなく、世界に通用する人材育成(例:ハーバード大)を目指す次元の話。
それでも東大が変革を選んだ理由
近年の少子化の影響で、国内受験者数は減少の一途をたどっています。とはいえ、東京大学に関しては他大学に比べて突出したブランド力と実績を持っており、全国からトップ層が集まる構図は今なお健在です。むしろ、他大学に魅力が乏しいからこそ、トップ層が東大に集中しているという側面すらあります。
その現状において、東大が「世界」に目を向けたのは自然な流れとも言えます。留学生の受け入れ、国際通用性のある教育体制の整備は、国際競争力の強化とブランド戦略でもあります。
さらに注目すべきは、高い学力層に一定数存在する「着眼点や発想の奇抜な人材」への期待です。筆者の体感としても、それらの生徒は学力という物差しでは測れない価値を持っています。
ただし、ここで重要なのは「時代が終わった」というよりも、「かつては学力の高い層を集めれば、おのずとユニークな学生が含まれていた」という構図が、少子化によって揺らいでいるという点です。つまり、現在は層が薄くなり、ユニークな学生が以前ほど自然に集まる状態ではなくなった。そのため、東大はあえてユニークな人材を積極的に取りにいこうとしているのだと考えられます。
「ユニークであること」への評価の転換
ユニークな人材がなぜ今、これほど重視されるのか——その背景には、現代社会の構造的な変化があります。
衣食住や社会的インフラの充実により、人間の基本的な生活は満たされつつあります。機械化や規格化の進展、さらにはAI技術の急速な発達によって、多くの作業や思考は「他者と同じであること」が効率的とされ、再現性の高い成果が重視される時代が続いてきました。
しかし、それゆえに、人と同じでは差別化が難しい時代になりつつあります。産業の寡占化、生活の定型化が進む中、人間は「規格外の存在」——つまり、珍しい発想、突飛な視点、人とは異なる価値観を自然と求めるようになります。
人類の進化の歴史を見ても、思いもよらぬ特徴が次の常識になることがあります。たとえば、首の長いキリン、ユーカリしか食べず20時間眠るコアラ、鼻の長いゾウなど。どれもかつては「異常」とも見える特性でしたが、それが種としての進化と繁栄のカギになってきたのです。
結びに:塾としてできること
このような時代の流れの中で、私たち教育者や学習塾は、点数を取ることはもちろんのこと、「点数を取らせる力」だけでなく、「発想力」「表現力」「社会を見る目」といった、より幅広い力を育む必要があります。そして、そういった力をつける方法は、まさに「学力をつける」ことにあると千尋進学塾は考えています。
「学力か、ユニークさか」ではなく、その両方を育てる教育のあり方を、私たちも模索していくべきではないでしょうか。
なお、エッセイにも学力は反映されますし、評価軸を明確にすれば点数化も可能です。東大の挑戦を応援するとともに、「(a, b) を通らない接線を解答しない」ことの大切さ——つまり、設問をしっかり読んでそこから逸脱しないという姿勢、そして学問の基本である論理と根拠を逸脱しない姿勢も、今後も伝えていきたいと考えています。
📚「差のつく!読解のチカラ育成講座シリーズ」記事一覧
- ① “国語が苦手”は勘違い?読解力の正体、教えます
- ② “読めてるつもり”が一番危ない!読み飛ばし世代に欠けている力
- ③ 応用問題が解ける子の秘密は“読む力”にあった!
- ④ 読解力は国語だけの話じゃない!算数・理科にも効く“読みの技術”
- ⑤ 説明文が苦手な子に足りないのは“読書”じゃなく“論理力”
- ⑥ 小論文・推薦入試で差がつく!読解力×論理力の真価とは
- ⑦ 本を読むだけでは“読解力”は育たない?間違った読解力の鍛え方
- ⑧ “選択肢の消去法”で点が取れない子へ。論理的に読む力、ついてますか?
- ⑨ 読解力は“後からでも”伸ばせる?苦手意識をひっくり返す塾のトレーニング
- ⑩ 読解力と成績の相関関係|トップ層が必ず持っている“読みの技術”